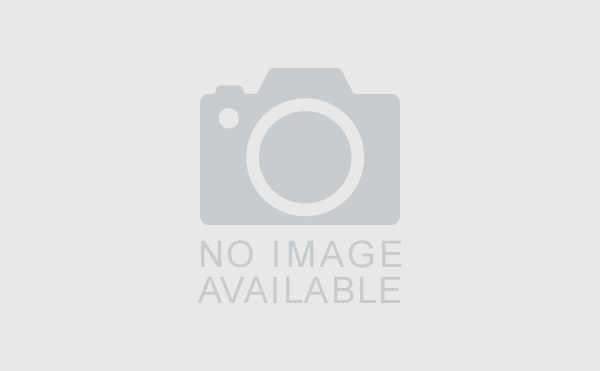蘊蓄;何故始業式は4月なのか?
日本での新しい年度の始まりは4月。 欧米では9月。 今日はこの違いの理由をお知らせします。
欧米の始業式が9月で、日本の始業式が4月である背景には、歴史的、社会的な理由が複雑に絡み合っています。
欧米の9月始業
- 農業との関係:
- かつて欧米では、子供たちが農作業を手伝うことが一般的でした。
- 特に、夏の収穫期は農作業が繁忙となるため、学校を休みにし、農作業が落ち着く9月から学校を始めるという習慣が根付きました。
- この習慣が、現在の9月始業の起源となっています。
- 米穀年度との関係:
- アメリカやイギリスなどでは、会計年度が10月から始まるため、これに合わせて学校の始業時期も9月に設定されたという説もあります。
日本の4月始業
- 会計年度との関係:
- 日本において、明治時代の初期には欧米の影響を受け、9月始業が採用されていました。
- しかし、明治19年に会計年度が4月から翌年3月までに変更されたことに伴い、学校の始業時期も4月に変更されました。
- これは、学校運営に必要な予算を政府から調達する上で、会計年度に合わせる必要があったためです。
- 慣習との関係:
- 4月は、桜の開花時期と重なり、入学式にふさわしいイメージがあるため、4月始業が定着したという説もあります。
- 国家試験との関係:
- 日本の国家試験が卒業シーズンにあわせて行われるものが多く、9月始業に変更するのが難しい現状もあるようです。
グローバル化の影響
- 近年、グローバル化の進展に伴い、海外の大学への留学や、海外からの留学生の受け入れが増えています。
- そのため、国際的な教育交流を円滑に進めるために、9月始業を導入する大学も一部で出てきています。
このように、欧米と日本では、それぞれの歴史的、社会的な背景から、始業時期が異なっています。
今日の蘊蓄でした。 さて、如何でしたでしょうか?
ではでは、また次回。